「最近の子ども、なんだか落ち着きがない…」と感じたことはありませんか?
朝はギリギリまで寝て、バタバタと登校。
帰ってくるなりゲームやYouTube。
夜はなかなか寝ようとせず、寝る直前まで画面とにらめっこ。
こんな子どもの姿に、モヤモヤしたことのある親御さんは多いのではないでしょうか。
ただ、最初にお伝えしておきたいのは
これは“子ども自身の問題”ではありません。
そして、あなたが「しつけができていない」わけでもありません。
実は現代社会の環境が、子どもたちから“ある大事な力”を奪っているのです。
それが「習慣力」。
習慣力とは、「行動を自動化できる力」
習慣力とは、「すべきことを、考えなくても自然にできる力」です。
たとえば、
- 朝起きたら顔を洗う
- 宿題を済ませてから遊ぶ
- 寝る前は映像コンテンツではなく読書する
こうした行動が「当たり前」として身についた子は、生活リズムも安定し、心も体も健やかに育ちやすくなります。
けれど今の子どもたちは、この「当たり前の積み重ね」を身につける前に、強い刺激と不規則な環境にさらされているのです。
なぜ?現代の子どもが“習慣力”を失っている3つの理由
刺激の強すぎる環境
スマホ、YouTube、ゲーム、タブレット学習。
子どもにとっては魅力的でやめられない刺激が、日常にあふれています。
こうした強い快感刺激は、脳の“やる気”や“自己制御”に必要な力を弱めてしまうことがわかっています。
やるべきことよりも、楽なこと・楽しいことばかりを優先するようになってしまうのです。
生活リズムの乱れ
夜遅くまで起きていたり、塾や習い事で過密スケジュールになっていたり。
こうした不規則な生活が、習慣形成の土台となる「決まった時間に行動する感覚」を奪っていきます。
脳にとっては「いつも同じリズム」がいちばん安心です。
リズムが崩れ続けると、自律神経も乱れ、落ち着きのない子になってしまいやすくなります。
親の“見本”が見えにくくなっている
親が仕事で忙しく、生活のリズムもバラバラ。
在宅ワークで部屋の中にいても、スマホやPCの前でずっと何かをしている。
これでは、子どもにとって「習慣のモデル」が見えにくくなってしまいます。
子どもは、言葉よりも“見て学ぶ”生き物です。
親が生活リズムを整えているか、画面ばかり見ていないか——
その“日々の姿”が、子どもの習慣力に大きく影響しています。
習慣は「叱るもの」ではなく「デザインするもの」
「早く寝なさい!」「またスマホ見てるの?」「なんで宿題やらないの!」
…そう言ってしまう気持ち、よくわかります。
でも、叱ることで習慣は身につきません。
むしろ、習慣とは「整えておく」ものです。
たとえば、
- 朝日が入るようにカーテンを少し開けておく
- リビングの一角に“読書コーナー”を作っておく
- おやつを「よく噛む系」のものにする(グミ、ナッツ、干し芋など)
- 寝る前は部屋の照明を間接照明にして、スマホではなく本を読んでみる
こうした小さな環境のデザインが、子どもにとっての「当たり前」を静かに変えていきます。
まとめ:「子どもにどうさせるか」より、「自分はどうか」
「親ができていないことを、子どもができるわけがない」
「親はやっていないのに、子どもだけに求めるのはおかしい」
あなたも、そう感じたことがあるかもしれません。
まさにその通りです。
子どもに「スマホはほどほどに」と言うなら、まずは自分が触らない時間を作ること。
「夜は早く寝よう」と言うなら、自分の生活リズムを整えること。
子どもにどうさせるかより、自分はどうか。
その姿こそが、子どもにとっていちばんの教科書になります。
次回予告
次回は、実際に私が意識している“夜の習慣デザイン”をご紹介します。
スマホを使わず読書をすることで、子どもたちの「夜の時間」がどう変わったのか——
リアルな家庭の実践からお届けします。


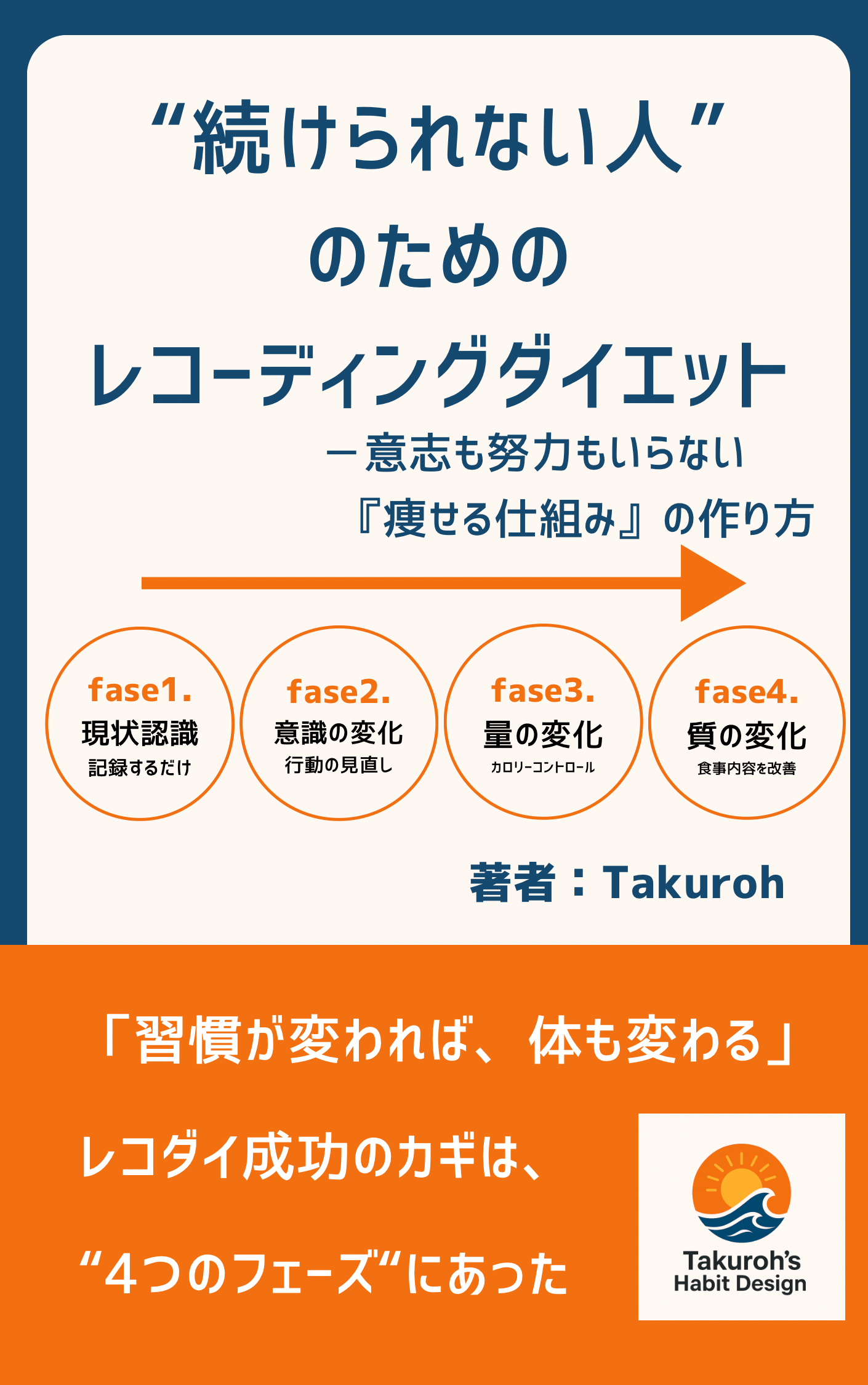

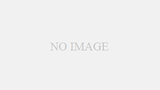
コメント